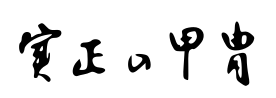2025年7月28日(月)
公式HPのギャラリーには沢山の逸品兜を掲載しております。
そのギャラリーに掲載している兜を例に、兜のことを詳しくお話ししていきたいと思います。
今回は星兜(ほしかぶと)についてです。
1分ほどでサクッと読める内容となりますので最後までお楽しみ下さい。
また弊社の兜だけでなく、お手持ちの兜やお目当ての甲冑にも共通するお話になります。
是非照らし合わせてご覧ください。
◆星兜って何を表しているの?
ギャラリーやYoutubeショートに掲載している甲冑をはじめとして、博物館などで展示されている甲冑の名前に星兜(ほしかぶと)と名の付くものがあります。
この星(ほし)とは、何のことか皆さんご存じでしょうか?

これは鉢の表面のゴツゴツとした鋲のことを指します。
◆星兜とは?
星(ほし)とは鉢に取付けられている三角錐状に尖った鋲のことを言います。
戦乱の時代、兜鉢を制作する際は矧板(はぎいた)という細長い鉄製の板を頭の形に合うように重ねて制作をしていました。
その重ね合わせた矧板(はぎいた)は鋲を叩き隣同士の板を固定する、いわゆるかしめて固定をしていました。
この鋲が時代と共に変化し、形を整え装飾と補強を兼ねた星(ほし)へと変化していきました。




また、星(ほし)で覆われた兜を総称して星兜(ほしかぶと)と呼びます。
武将で例えますと、徳川綱吉などが自身の甲冑に取り入れています。

同じ星兜でも大きな星を大胆に配置する鉢もあれば、米粒大の小さな星を隙間なく敷き詰めている鉢まで多岐に及びます。
どうして同じ星兜(ほしかぶと)なのに見た目に特徴や違いが出るのでしょうか?
そこに歴史が隠れています。
※注記:この後、星(ほし)の数を時代ごとに計算をしたものが登場します。
本来ならば史料や文献を基に正確な数字を出すべきところですが、多くの方にイメージしていただきやすいように間数と一行の個数を単純に掛け算をして出しております。
計算で出た数以外にも、正面の矧板(はぎいた)は数行かしめることや腰巻き部分にも星(ほし)がかしめられることを注記にてご説明させていただきます。
予めご了承ください。
◆星兜の歴史
平安時代頃から鍛鉄技術の発達により、より大きな鉄の板をより大きな鋲で留めて作る事が可能になりました。
この時代は大星(おおぼし)と呼ばれる大きな星が使用され、一行に5~9個の星(ほし)がかしめられているのが特徴です。
厳星兜(いかぼしかぶと)などにみられる質実さと力強さはまさに平安時代を象徴しています。
あくまで目安ですが、18間の鉢に一行9個の星をかしめたとして、単純計算で162個の星が使われました。
鎌倉時代に入ると星(ほし)の大きさが段々と小さくなり、中星(ちゅうぼし)や小星(こぼし)と呼ばれるようなものが使われるようになりました。
技術の向上と美観的要因によってかしめる数も増えていき、鎌倉時代頃で一行に10~16個の星(ほし)がかしめられました。
こちらも目安ですが、30間の鉢に一行16個の星をかしめたとして、単純計算で480個の星が使われました。

南北朝時代に入ると星(ほし)は更に小さくなり、米粒大の大きさの星(ほし)まで登場しました。
数も格段に増え、一行に30個も打ち付けてある兜も出てきました。
更に南北朝時代は62間(ろくじゅうにけん)のような間数の多い鉢も登場したときでもありました。
62間の兜に一行30個の星(ほし)をかしめたとして、単純計算で1860個の星が使われていました。

お手持ちの兜を見る際は、星(ほし)の大きさや数にも是非注目してみてください。
最後までご覧いただきありがとうございました。