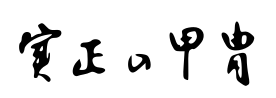実正の甲冑公式HPには、三世別所実正が彫金をしている写真を掲載していたり、
ギャラリーの説明文にもたくさん彫金という言葉が登場します。
またYouTubeでは、実際に実正が彫金をしている動画を公開しております。(Part.2、3)
言葉は聞いたことあるけど、彫金ってなんだろう?実際どのようにやるんだろう?
本日は彫金についてお話していきます。
◆彫金ってなに?
百聞は一見にしかず。
まずは言葉で説明するよりも、ご覧いただいた方が早いかと思います。
以下に動画と画像をご用意しましたので、是非ご覧ください。
※下のボタンを押すと、彫金の工程から再生されます。(新しいタブが開きます。)

彫金(ちょうきん)とは、鏨(たがね)と金鎚を用いて金属を彫っていく技法のことを指します。
貴金属をはじめとするアクセサリーや、刀剣や刀装具にも使われ、現代でもよく目にする技法のひとつです。
※ 彫金には本来、表面に凹凸を付ける技法も含まれますが、今回は「彫る」に限定してお伝えしていきます。
鏨(たがね)とは鋼で出来た棒状の刃物のことで、先端が様々な形をしているのが特徴です。
「毛彫り鏨」や「片切り鏨」など、彫るだけでも何種類もあります。
金鎚は釘を打つ時に用いる重たい物ではなく、小ぶりの「おたふく鎚」というものを使用します。
手元にあるおたふく鎚のひとつを、実際にはかりで計測すると約77g。
身近なもので例えると、スマートフォンが約150~200g前後なので、その半分くらいの軽さの金鎚になります。
片方の手でタガネを握って刃先が自分に向くように構え、
もう片方の手で金鎚を持ち、タガネの頭を叩いて金属を彫っていきます。
一打で1mm進むか進まないかの距離を、淡々と彫り進めていきます。


しかしこれでは両手が塞がってしまい、彫りたい金属が動いてしまいます。
そこで、写真にも写っている黒いあるもので固定をします。
さて、この黒いあるものの正体を、皆さんご存じでしょうか?
答えは松ヤニというものを使用します。
松ヤニとは、
・松脂(まつやに:松の幹から分泌される天然樹脂)
・地の粉(じのこ:焼いた粘土や瓦を粉砕したもの)
・なたね油などの植物油
これらを混ぜ合わせた物を言います。
松ヤニの熱すると液体になり、冷めると固まる性質を利用して金属を固定します。
また、熱する際に放つ独特の匂いも特徴の一つです。しっかり換気をしていきます。
冷ますと言っても冷蔵庫などに入れる必要はなく、常温または水を少しかけてしばらく待つと固まります。
ちなみに、たばこのヤニを想像する方もいらっしゃるかと思いますが、それとは全くの別物になります。
◆彫金ってなんだか簡単に出来そう?
ここまで彫金の説明や使用する道具、手順のお話しをしてきました。
工具や道具を専門店で揃えたり、火を使ったり換気をするなど設備を整える必要性がありますが
そこをクリアしてしまえば、案外簡単なんじゃない?
だって実正さん、簡単そうに彫ってるし…
確かに手順は簡単です。器用な方ならコツをつかんで彫れると思います。
しかし、まっすぐで綺麗な線を彫るとなると一筋縄ではいきません。
均一な太さにならない、彫り終わる前に途切れてしまう、自分の思った方向に進んでくれない、
ときには金鎚がタガネに当たらず、自分の手を打ってしまうこともあります。
また工具のお手入れも欠かせません。
包丁を使い続けると切れ味が悪くなるように、鏨も長く使っていると段々と切れ味が悪くなってしまいます。
切れ味を取り戻すために砥石で研ぎ直しますが、
やはり包丁と同様、一定の角度をキープし続けないと逆に刃先がなまってしまいます。
実正曰く、
「練習と鍛錬、何事もすぐには出来ないし、いつでも練習してないと…」
「細く長く練習を続け【手が決まる】ことで美しい線が描ける…」
とのことです。
彫る際も研ぐ際も【手が決まる】事が大切になってきます。

文中でもお話ししたとおり、甲冑に限らず様々なものに彫金が施されています。
皆さんの周りの「彫金」を是非探していただき、その技術や美しさに触れてみてください。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。