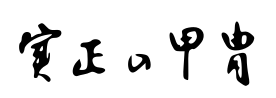ギャラリーの甲冑やYouTubeやブログに、「かしめる」というワードが沢山登場します。
「カシメ」とも言いますが、これはどういう意味かご存じでしょうか?
本日はカシメについてお話しさせていただきます。
1分ほどでサクッと読める内容となりますので最後までお楽しみください。
◆カシメとは?
カシメとは、穴のあいた板状のものを重ね、リベットと呼ばれる金属部品を差し込み、それを叩き変形させて固定する技法です。
溶接・接着剤・ネジ・ボルトなどを使用せずに2枚の板を締結できる加工方法で、かしめるとも言います。
身近な物では革製品やランドセル、ファイルやバインダーなどに使われています。




もっと大きなものだと、あの東京タワーも部品同士を固定させる為にこのカシメの技術を施しています。




◆兜との関係は?
東京タワーにも使われているカシメの技術は、兜のどこの部分に使われているかご存じでしょうか?
正解はここ、鉢の部分で使われています。
(写真は、阿古陀形 打出の小槌前立 四十六間総星兜)


戦乱の時代、兜の鉢を制作する際は矧板(はぎいた)という細長い鉄製の板を頭の形に合うように重ねて制作していました。
この矧板(はぎいた)を固定する際にカシメを施しています。
穴をあけた2枚の矧板(はぎいた)を重ね合わせ、重なった穴の部分に星(ほし)という三角錐状の鋲を入れ、叩いて固定します。

◆実際にどうやってかしめるの?
百聞は一見にしかず。
言葉で言うよりも実際に動画や写真で見ていただいた方が分かるかと思いますので、順を追ってご説明いたします。
まず、動画で一気見したい方は下記のリンクよりご覧いただけます。
まずは星(ほし)の台を万力に設置します。
台が垂直になるように微調整も行います。

台のくぼみに星(ほし)を入れます。
写真の星(ほし)は米粒大ほど。あまりの小ささに床に落としてしまうこともあります。
指先の感覚を頼りに、台のくぼみに置きます。





そして鉢のかしめたい箇所の穴に星(ほし)の足を差し込みます。
このとき、鉢と星(ほし)の接地面がまっすぐになるように注意します。
曲がった状態でセットをすると、斜めに取り付いてしまいます。




そして支える手で鉢をしっかりと持ち、差し込んだ足を金鎚で叩きかしめます。
ちなみに星の足は直径1.0mmほどしかありません。
外して鉢を打ってしまうと、鉢自体が変形してしまいます。
他の場所に当てないよう集中してかしめていきます。




この順序で1個ずつかしめていきます。
星(ほし)は1個かしめて終わりではありません。1つの鉢につき100個近い数を、多いもので2,000個以上の星(ほし)をかしめていきます。

「機械で一気に取付けてるんでしょ?」と思われがちですが、実正の甲冑では一つずつ手作業でかしめています。
是非、手作業の温かさを味わっていただきたいと願っております。
最後までご覧いただきありがとうございました。