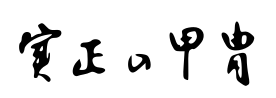– 代表挨拶 –

– 実正の拘り –
「実際の兜と同じように作りたい」
三世 別所実正がかねてより抱いていた想いから、この逸品兜は生まれました。
三世 別所実正がかねてより抱いていた想い
から、この逸品兜は生まれました。
「同じように」とはどういう事か?
まず平らな真鍮板に矧板と呼ばれる部品をけがく(線を書く)
ことから始まります。
1つの鉢に何十というそれをけがき、切り出し、アールを付け、
端に折返しを付け強度を出し、1枚ずつ星でかしめていく・・・
更に兜は鉢だけでは成り立ちません。
しころや吹返を矧板と同様に平らな銅板にけがいていきます。
ここからは職人の腕の見せ所。
立物や装飾はユニークな発想や意匠を凝らした技術によって
美しく表現されていきます。
まず平らな真鍮板に矧板と呼ばれる部品を
けがく(線を書く)ことから始まります。
1つの鉢に何十というそれをけがき、
切り出し、アールを付け、
端に折返しを付け強度を出し、1枚ずつ星でかしめていく・・・
更に兜は鉢だけでは成り立ちません。
しころや吹返を矧板と同様に平らな銅板にけがいていきます。
ここからは職人の腕の見せ所。
立物や装飾はユニークな発想や意匠を
凝らした技術によって
美しく表現されていきます。


なぜこだわった兜を作るのか?
ここで実正が幼少の頃から大好きな昆虫のお話をさせてください。
昆虫は一般的に脚が6本、体は頭・胸・腹の3部分で構成されています。
そして小さいことを理由に脚が4本で体は2部分でというように
省かれることはありません。
必ず脚は6本、体は3部分の構成です。
翅も同様です。
ここで実正が幼少の頃から大好きな昆虫のお話をさせてください。
昆虫は一般的に脚が6本、体は頭・胸・腹の
3部分で構成されています。
そして小さいことを理由に脚が4本で
体は2部分でというように
省かれることはありません。
必ず脚は6本、体は3部分の構成です。
翅も同様です。
話を戻して甲冑はどうでしょうか?
手間の省略やコストカットの観点から、
本来あるべきしころの段数や星の数を極端に減らしたものや
明らかに粗雑なつくりのものも見受けられます。
勿論それら全てが悪いというわけではありません。
では、
「後世に良いものを残したい」
「次の世代に語り継ぎたい」
と考えたとき、果たして
それらに甘んじるばかりで良いのでしょうか?
手間の省略やコストカットの観点から、
本来あるべきしころの段数や星の数を
極端に減らしたものや明らかに粗雑なつくりのものも見受けられます。
勿論それら全てが悪いというわけでは
ありません。
では、
「後世に良いものを残したい」
「次の世代に語り継ぎたい」
と考えたとき、果たして
それらに甘んじるばかりで良いのでしょうか?

半世紀以上にわたり甲冑制作を続け、
⾧年の研究と鍛錬を重ねることで培った確かな技術と豊かな表現力。
半世紀以上にわたり甲冑制作を続け、
⾧年の研究と鍛錬を重ねることで培った
確かな技術と豊かな表現力。
そして職人としての矜持が
そして職人としての矜持が
「実際の兜と同じように作りたい」
冒頭のこの言葉を、単なる願望から使命へと突き動かしていきました。
節句人形・五月人形の枠を越えて美術品として親しんでいただくとともに、
その高度な技術と表現に触れていただきたいと願っております。
冒頭のこの言葉を、単なる願望から使命へと突き動かしていきました。
節句人形・五月人形の枠を越えて美術品
として親しんでいただくとともに、
その高度な技術と表現に触れていただきたいと願っております。

– 三世 別所実正 –

| 昭和29年(1954) | 東京浅草に生まれる |
| 昭和47年(1972) | 父親である二世実正(別所正二郎)のもと甲冑製作に従事 |
| 昭和58年(1983) | 三世別所実正を襲名 |
| 平成24年(2012) | 多太神社蔵 斎藤別当実盛公兜を復元製作 |
| 平成29年(2017) | 人形の東玉(さいたま市)にて三世別所実正展を開催 |
– 略歴 –

室町時代から戦国・江戸時代にかけて、
主に阿古陀鉢に感銘を受け、製作工程を
忠実に再現するべく研究を重ねている。
20歳頃、研究のため博物館に赴いた際
展示してあった六十二間の兜の形や美しさに感銘を受ける
あまりに圧倒され、当時は作ることさえ考えなかったが
それでもあの美しさを表現したく
幾度となく試行錯誤を試みた末に
六十二間の兜の完成にたどり着いた


そこに自身の積み重ねてきた緻密で卓越した職人技と
ユニークな発想を組み合わせ
逸品兜を制作・発表
節句人形・五月人形の枠を越え
美術品としても評価を受けている

室町時代から戦国・江戸時代にかけて、
主に阿古陀鉢に感銘を受け、
製作工程を忠実に再現するべく
研究を重ねている。
20歳頃、研究のため博物館に赴いた際
展示してあった六十二間の兜の形や
美しさに感銘を受ける
あまりに圧倒され、
当時は作ることさえ考えなかったが
それでもあの美しさを表現したく
幾度となく試行錯誤を試みた末に
六十二間の兜の完成にたどり着いた


そこに自身の積み重ねてきた
緻密で卓越した職人技と
ユニークな発想を組み合わせ
逸品兜を制作・発表
節句人形・五月人形の枠を越え
美術品としても評価を受けている